
アペックス便り12月号
●〖締めくくりの力〗一年の終わりに立ち止まる
12月になると街の空気がわずかにざわつき始める。年末の足音、受験の足音、寒さの足音──いろいろな「締めくくり」が同時に近づいてくる時期だ。一年を振り返ると、子どもたちの顔つきが春とは見違えるほど変わっている。学力という数値以上に、目の奥の「覚悟」のようなものが宿り始める。
しかし、その変化はある日突然訪れるわけではない。むしろ、毎日の小さな積み重ねの中で、気づかないうちに育っていくものだ。
時代はますます速く、慌ただしくなっている。
情報も、流行も、価値観さえも、少し目を離せばすぐ入れ替わる。そんな中で、私たちはつい「結果」ばかりを求めてしまうが、子どもたちの成⻑は本来もっと穏やかで、もっと深い営みのはずだ。だからこそ、年の瀬のこの時期に、一度立ち止まってみたい。
「この一年、自分は何を続け、何を乗り越えたのか」「どんな小さな芽が育ち、どんな一歩を踏み出せたのか」
締めくくりとは、ただ終わらせる作業ではない。むしろ、「次に向かうための余白」を整える行為なのだと思う。大掃除をすると、新年の光が部屋に入りやすくなるように、心の棚卸しをすると、新しい挑戦のスペースが自然と生まれてくる。
受験生にとっては、いよいよ本番が近づく季節。
焦りや不安が出てくるのは当たり前だ。でも、不安は「本気で向き合っている証」でもある。
大切なのは、それを否定せず、丁寧に抱え込むことだ。足元の一歩を踏みしめながら、静かな呼吸で前に進んでいこう。そして受験生以外のみんなにとっても、12月は一年を味わう大切なときだ。時間は速くても、心のリズムは自分で整えられる。慌ただしさの中に、ほんの少しの“静けさ”を忍ばせてみる。
その習慣こそ、来年の自分を大きく支える土台になるはずだ。今年もあとわずか。最後まで、誠実に、一歩ずつ。そして、来年の自分に少しだけ期待しながら、この一年を静かに締めくくろう。
…[次回に続く]
おしらせと今月の予定
憲政初の女性総理の高市新政権がスタートして一か月経ち、巷では早くも師走のムードに拍車を掛ける様に、イルミネーションに彩られ、暑かった秋も思い出したかのように寒さが増すとともに木々は紅葉して駆け足で冬を迎えようとしています。高市総理の台湾有事への発言に過剰に反応した中国の反発による日本への渡航規制や輸入規制等、お互いが振り上げた拳を降ろすのに四苦八苦しているが、歩み寄る為にはメンツを脇に置いて、話し合う手立てはないものか…厄介なムードである。
今月の予定
○12/9日〜20迄 三者懇談会(要予約)
○24日〜1/8迄 冬期講習会(受験生必修)※非受験生は希望制です。
◆冬季強化合宿(受験生必修)※講習会、合宿共に外部生徒の参加も可能です!真剣なお友達を誘ってみよう!!
アペックス便り バックナンバー
| 2025年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2024年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2019年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2018年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2017年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2016年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2015年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
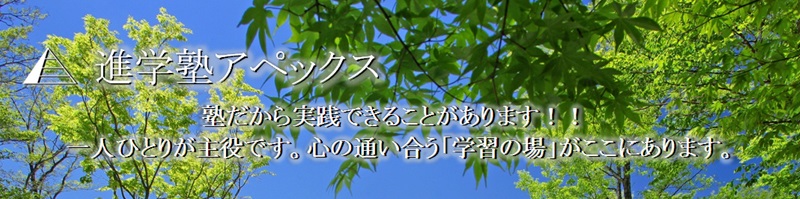
 ごあいさつ
ごあいさつ